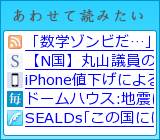久々に「トランス」を聴きました。
最近はプログレッシブ~エレクトロなハウスを中心に音源を漁っていますが、一時トランスに傾倒していた時期があります。system-Fの「out of the blue」(*1)がいろんな所でかかりまくっていた時期ですね。2000年か。
あの頃のイベントでは、ハードハウスのDJもテクノのDJも、みんながピークタイムでトランス(ぽいモノも含む)を掛けていましたからね。
でも「out of the blue」は直ぐに聞き飽きてしまったなあ。で、そのうちにトランスの多幸感だけを凝縮した「アゲアゲ」な音でギャル達がパラパラを踊るようになってから(*2)はオジさんは付いて行けなくなり、ゴアやサイケに逃げ込んでしまいました。
ゴアトランスやサイケデリックトランスは好きです(*3)。
グイグイと引っ張るボトムとか攻撃的に鳴るシンセとか、「多幸感を排除」して「音でトランス状態に持って行く」というトランス本来のスタイルを頑なに守っているジャンルだと思うんだ。
そんなゴア・サイケな匂いを発していたらサイケデリックトランスのイベントに(*4)、VJのお誘いを受けましたね。懐かしいな。
さて、今回紹介するのは、「Your Dawn」:The Originators Featuring Tomomi Ukumoriです。
自分音楽史で、2007年の3大ニュースは「Perfumeとの再会」と「CHERRYBOY FUNCTIONの発見」そして「Tomomi Ukumoriとの出会い」ですからね。今作は今年の締めに相応しいリリースです。
The Originatorsは日本のトランスシーンにおいて注目を浴びている人達のようです。
って、正直「ギャルトラ」とか「ブチアゲ」のおかげで、私自身が日本のトランスシーンに対して偏見を持っていて、シーン自体を全く注視していないので良く解らんのですわ。Tomomi Ukumoriと絡んでいなければ聴く事は無かったかもしれない。でも、The OriginatorsのオリジナルMixはずっしりと重量感のある仕上がりで、ユーロトランスの流麗さにサイケデリックトランスの攻撃性が加わったような印象で、好感が持てました。機会があれば別の音源も聴いてみたいと思います。
そういえばパフュもトランスやってたよね。黒歴史にされているけど(笑)。
Tomomi Ukumoriのコレは黒歴史どころか彼女の代表作としてコレクションされるべき内容。
(BGM 「Your Dawn(Tomoya Tachibana Remix)」:The Originators Featuring Tomomi Ukumori)
注釈:
(*1)邦題は「蒼き彼方に」。このセンス、シブすぎ(笑)。アルバム自体は良い出来だと思う。結構、良曲多いし。
(*2)それ以来、「アゲアゲ」だとか「ブチアゲ」が日本におけるトランスの代名詞になってしまったのだろうか? そっち方面はホントに苦手。「多幸感の大安売り」は生理的に受け付けられない。
(*3)Juno ReactorとかX-Dreamとか今でも聴きますね。一時期、ネット上に散らばるゴア・サイケのMP3ファイルを漁りまくった事があります。Astral Projectionとか。
(*4)早くから新潟でトランスを専門に回していた「小ちゃくてキュートな女の子DJ」TAMAちゃんとか、パーティオーガナイズチーム「RAYOK」のKABUさんや、サイケデリックトランス・レーベル「Psyristor Trax」(http://psyristor.com/)のTatsuo(Charm)さんにはお世話になりました。新潟でPsyristor Trax関連のリリースパーティをやるときは、ほぼ専属でVJをやらせてもらいました。いやあ、楽しかったです。
LSTDのVJ履歴(http://www1.linkclub.or.jp/~panchos/vj/index.html)
追記:
Tomomi Ukumori繋がりで、ネタをもう一つ。
彼女のデビューアルバム「indigo」のトップを飾るセンチメンタルなナンバー「Eyes On You」をポップでトライバルでエレクトロな哀愁のピアノアンセムに仕上げた 「Eyes On You Lag Stage Remix」がiTunesで配信されています。コンパイルしたDJ Heavygrinderのキュートでセクシーな小悪魔振りにも注目(謎)。
http://phobos.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewAlbum?id=266721352&s=143462
今年の夏、“キリン・ザ・ゴールド”のCMでbirdがカバーしたマルコス・ヴァーリの名曲「BATUCADA(バトゥカーダ)」を耳にした人は多い事でしょう。
BATUCADAを聴いて「おおっ、コレは懐かしいな」と思ったあなたは、クラバー暦10年以上ですか? 前世紀末前後のハウス系パーティのフロアで「BATUCADA」でひとしきり盛り上がった人ですね。
はい、そんなアナタに今日は懐かしのSpillerカバーによる「BATUCADA」です。
ちょうどbirdによるカバーがCMで流れ始めた(と言うか話題になった?)今年の7月に再発されていたんですね。うかつでした。最近ようやく再入荷にありつくことが出来ました。
私は、DJを始めるに当って揃えたい音源(*1)にSpillerのBATUCADAが有ったのですが、どこのレコ屋サイトでも見つけることが出来ませんでした。たまに、ヤフオクで出品されるくらいでしたね。
この曲は、VJを始めた当時、ハウスDJ達がピークタイムに競って回すくらいの定番でした。実の所、VJを始めた頃はそれほど四つ打ち音楽に傾倒していなくて、現場でハウスを聴いていても「右から左へ受け流す」状態でした。でも、この曲は自分でも凄くハマって、曲のイメージに合わせたVJネタをいくつも仕込みました。
たぶん、ハウス好きになるきっかけの曲だったのかもしれません。
|
「Batucada」:Spiller |
さて、再プレスされたこのレコードですが、管理がずさんなのでしょうか? あんまり品質がよろしくないのでがっかりでした。思いっきり反り返っていたんですね。まあ、ちゃんと掛けられるんですがね。
結局デジタルで取り込んで、CDに焼きました。意味ねえ。
ちなみに、マルコス・ヴァーリによる「Batucada」はiTunesで試聴・購入できます。極上のお洒落ボッサでマターリできます。おすすめ。
(BGM 「BATUCADA (Elllusive Samba Vocal)」 : Spiller )
注釈:
(*1) ハウスにハマるきっかけの「Batucada :Spiller」の他は、デトロイトテクノのスタンダード「Jaguer : DJ Rolando」と「Hi-Tech Jazz : Galaxy 2 Galaxy」。さらに、プログレッシブおやじの原点「SCORCHIO : SASHA / EMERSON」。以上4アイテムは揃えたいと思っていた。
しか~し、アナログが再発されたのはBatucadaとJaguerのみ。他は音源がCD化されているので、探せばあるんだけどね。Hi-Tech Jazzは「Hi-Tech Jazz Compilation」というタイトルのMad Mikeベストとも言うべきCDが出ているので、それを買いました。しかし、 問題は「SCORCHIO : SASHA / EMERSON」だね。これはCDシングルが廃盤になっていて、AMAZONでは結構いい値段で中古が出ている。「¥4,676より」ってなんだよ。かわねーよ。
どうも、プログレッシブ親父です。ようやくOMBの新作「FRAME」をレビューします。
噂のテクノポップ・アイコン「Aira Mitsuki」さんもお薦めしている「FRAME」ですね。
先ず、リリース時に上げたエントリで、「プログレッシブ・ハウスって10代の女の子が聴く音楽じゃないだろ?」などと不適切な表現をしてしまった事について、お詫びいたします。申し訳ないと、、。
私の想像ですが、Aira Mitsukiさんは多分ギャルトラに飽きてしまい、「多幸感で無理やりイカされるのは、もう嫌!」と、ミニマル、クリック・ハウス経由でプログレッシブ・ハウスにたどり着いたのでしょう。それならば解ります。心を落ち着ける場所が欲しかったのですね。
「ようこそプログレッシブな世界へ。心より、歓迎いたします。」(、、、笑。俺って何者?)
私が考えるプログレッシブとは。
例えば、テクノがビートに乗り、ハウスがグルーブに乗るとすると、プログレッシブは(それがプログレッシブ・ハウスだろうがプログレッシブ・トランスだろうが)音に包まれる感覚。テクノやハウスが昂揚感でイクものだとすると、プログレッシブは音に身を委ねて連れて行ってもらうって感じ。解るかなあ? 上手く伝わらないけど、そんなイメージで捕らえている。
さて、私とOMBさんとの接点ですが、かなり過去に一度、イベントで御一緒した事があります。OMBさんがANOYOに所属していた頃ですね。しかし、非常に爆弾発言なのですが、「ゴメンなさい。印象に有りません。」
ってえーっ?!(*1)
おいおい、、。
DJ初心者として今年の始めに音源を買い揃えた中で、OMBの「Perfect Island / Taji Mayer」があります。シスコのサイトで試聴して購入したのですが、この音世界にかなりハマってしまい、それ以来リリースを追いかけています。ただ、過去のリリース音源はなかなか入手困難なので、今回の新作は特に期待していました。
OMBの良さは「音」。Aira Mitsukiさんも「シンセ音が良い」って言ってましたが、的を得てますね。空間を音で埋めるのではなく、無限に広がる空間に音を解き放って行くような、そんな感じ。音の一つ一つの粒がしっかり主張していて、実に美しいんですわ。
|
「FRAME」:OMB このアルバムは「聴きやすさ」を意識した仕上がりになっていると思います。 |
さて、Aira Mitsukiさんは「VILLALOBOS」と「OMB」でテクノポップアイコンとして音世界を探求中。
Perfumeは?
樫野さんは「InK」と「KASKADE」。女子大生としての正常進化だな。
大本さんは「Ryukyudisko」と「Halfby」か。これはテクノポップ・ユニットとしての正常進化だな。
西脇さんは「Aiko」と「スキマスイッチ」か。アイドルとしての正常進化なのか?
うーん、エレクトロ濃度が足りないですね。そこで、あ~ちゃんに是非お薦めしたい一曲があるのですが、それは、あしたのココロだ。多分ね。
注釈:
(*1)これについて弁明させて欲しいのですが、そのイベントは野外レイヴで、私はVJとして参加したのですが、日没から日の出まで約9時間に渡って一人で映像を回さなければならないという非常に過酷なものでした。曲が掛かると瞬時にその曲の世界観をイメージしてそれに合うVJネタを10~20ほどセレクトし、それらをテンポ良く切り替えたり、曲の展開に合わせてリアルタイムでエフェクトを掛けたりと、1曲のうちでもやる事は盛り沢山なのね。集中力が続いても2時間が限度だし、トイレにも行きたいし、喉も渇くし、おなかも空く。電源が落ちそうになったり、風でブースのテントが飛ばされそうになったりと、トラブルも起きる。そんなかんなで夜が明けると疲労困憊。音など何も憶えていないんですねコレが。
通常、長時間のイベントでは複数のチームで交代しながらやったり、別のVJにサポートをお願いします。フロアに降りて踊ったりして雰囲気を確認したり、ラウンジでなじみのお客さんと会話をして気分転換しながら、映像を回すための集中力を高めるのですね。ところが、その日のイベントでは、サポートをお願いしていたVJに別のイベントが入って参加できなくなってしまい、結局一人でやる羽目になったのですね。映像回している時はリズムに乗って腕を振り回す勢いでVJ機材を操作しているんですが、ホントにテンパっていると、まるで印象に残らないのね。イベントはお客さんとして遊びに行くに限るわ。
Perfume『ファン・サーヴィス[bitter]』のブックレットの最後にこんな写真が載っている。
ペダル・エフェクターってギター小僧には思いっきりツボだ(*1)。
バンマス - 「ソロんとこ、もうちょい『あ~ちゃん』効かせた方が良くね?」
ギター小僧 - 「くどすぎないか?」
バンマス - 「くどい位が良いんじゃね?」
ギター小僧 - 「了解。じゃ頭からもう一回行ってみようか!」
みたいなシーンが頭の中に浮かんだ。
バッキングパートからソロパートに移る前。オーバードライブのベダルスイッチを踏込む瞬間の緊張感と昂揚感。身体が熱くなる時。
バンドをやっていた10代の頃を思い出した。
最近はDJ修行の毎日で4つ打ち三昧。当然、回していて気分が乗らない時もある。そんな時はロックDJになったりする。
Hi-STANDARDから始まって、RANCID、Green Day、OFFSPRING。途中Rage Against the Machineへ寄り道したり、Jam、Policeとかの「懐メロ」に浸りながら最後はFoo Fightersで締めるみたいな。
たぶんこれは血中の「ディストーション濃度」や「ビート濃度」とかの「ロック成分」が足りなくなって、無意識に身体が要求しているんだな。
Foo Fightersの新作「Echoes, Silence, Patience & Grace」を聴いた。嫁にせがまれて購入したのだが、Foo Fightersは以前から良く聴いている。
Foo Fightersを知ったのは「Learn to Fly」。ビデオのバカさ加減とデイヴ・グロールの芸達者ぶりに笑った。
グランジの盛り上がりが最高潮に達していた頃、私はAcid Jazzにどっぷりと傾倒していたので、ニルヴァーナの名前は聞いても音そのものを聴くきっかけが無かった。そのため、デイヴ・グロールの存在も知らなかったし、Foo Fightersは「どっかから沸いて出てきたバンド」くらいの認識しかなかったのだが(爆)。
|
「Echoes, Silence, Patience & Grace」 : Foo Fighters |
Foo Fightersの良さって、圧倒的な存在感と安定感による「どっしり構えたギターサウンド」に有るかな。それと、フロントマン「デイヴ・グロール」のカッコよさ(*2)だな。2000年のフジロックで初めてライブを体験して実感した。
うーん、まったく新作のレヴューになってないな(爆)。
注釈:
(*1) コレをモチーフにTシャツを作ろうと図案を考案中に、「B U P P A N !!」さんのところで先を越されてしまったので諦めました。
http://d.hatena.ne.jp/pinksun/20070425
http://d.hatena.ne.jp/pinksun/20070927
なかなか良いですね。
(*2) クイーンズ・オブ・ザ・ストーン・エイジのサポートでドラムを叩いていた姿の方がカッコ良いと感じたのは、私だけだろうか?
派手さは無い。至ってシンプル。
「Radio Edit」は程好くポップ。前作の「Two Months Off」ほどのHeavenlyさは無い。
Remixは間違いなくフロア・チューン。私はエレクトロ・ハウスな「Pete Heller Remix」がツボ。
「Oliver Huntemann Remix」はミニマルな感じ。ケミカルの「We Are The Night」でも感じたんだけど、最近の流れなのかそっちの方向に皆が向いているような気がするのは私だけ?(*2)
|
1. Crocodile (Radio Edit) |
そう言えば、昨晩、日本テレビの「NEWS ZERO」でUnderworldが特集されていましたね。正直驚きました。夜のニュース番組の枠組みの中でクラブカルチャーが語られるなんてねえ。Underworldの音楽面だけではなく、TOMATO(*1)としての活動内容や日本企業との繋がりもちゃんと押さえてありましたね。カール・ハイドへのインタビューも含め、Underworldを知らない人に紹介する内容としては良く纏めてあったと思います。
注釈:
(*1)アートイベントでよくお世話になった新津市美術館(現 新津美術館)の学芸員の方が居るのですが、その人に「TOMATOの企画展やりましょうよ」と口説いていたっけなあ。「TOMATOを呼べるのは新潟にスタジオ・アッズーロをつれてきた新津市美術館さんしか居ませんよ!」ってね。確かにそうなんだわ。新津美術館は結構「おっ?!」と言うような企画展をやってくれるのでね。「新津美術館の裏のすり鉢状の円形野外劇場で音楽(Underworld)とアート(TOMATO)のインスタレーションをやるとハマるだろうなあ」と妄想していた。
(*2)Oliver HuntemannはケミカルのDo It AgainもRemixしていたのね。今気づいた。
http://www.cisco-records.co.jp/html/item/003/024/item279520.html
| 01 | 2025/02 | 03 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
困った事にPerfume成分が多目です。彼女達の親御さんとは間違いなく同世代です。ちなみにP.T.A.会員です。
ホントに御免なさい。
御用命は「lstd_rd の yahoo.co.jp」まで。