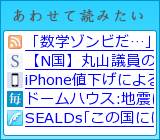以前のこのエントリでいっぱいいっぱい。あの時代をリアルタイムで生きていながら、YMOにはそれほどハマっていなかったのね。なので、今日はYMO結成前夜にリリースされた3枚のアルバムの話でも。
YMOのファーストアルバム「イエロー・マジック・オーケストラ」は1978年の11月にリリースされましたが、同年にYMOに先駆けて細野晴臣、坂本龍一、高橋幸宏がそれぞれソロアルバムを発表しているのですね。
実際にはその3枚のアルバムには3人が何らかの形で関わっているので、既にYMOのプレ活動が行われていたと見ることも出来ます。いずれにしても、その3枚のアルバムはそれぞれの代表作として語られる存在であると同時に、日本のポップスの歴史に於いて重要な位置を占めていると思います。
* * * * *
「はらいそ (PARAISO)」 : 細野晴臣 (1978年4月25日リリース)
「はらいそ」は、従来の細野さんの楽園主義を突き詰めて、来るべき電子の時代を先取りしたエレクトリックなグルーヴを感じさせてくれる快作でした。
ちなみにこのアルバムのリリース名義は「ハリー細野とイエロー・マジック・バンド」で、アルバムB面最後に「この次はモアベターよ!」の台詞が唐突に入っていました。細野さんから見てこの次に位置するアルバムがYMOのデビュー作なんですが、当時既に予測していたのかな。
Haruomi Hosono - Tokyo Rush -
Haruomi Hosono - はらいそ -
|
「はらいそ (PARAISO)」 : 細野晴臣 |
|
 |
Track List |
* * * * *
「千のナイフ」 : 坂本龍一 (1978年10月25日リリース)
「千のナイフ」は、坂本龍一のデビューアルバムです。
それまでの山下達郎の歴史的なライブ盤「IT'S A POPPIN' TIME(これも78年リリース)」でのセッションや数々のスタジオワークから、フュージョン系のファンキーなアルバムなのかなと思ったら、想像を遥かに超えた電子楽器による現代音楽とポップミュージックの融合で、当時は本当に度肝を抜かれました。
Ryuichi Sakamoto - thousand knives -
Ryuichi Sakamoto - plastic bamboo -
|
「千のナイフ」 : 坂本龍一 |
|
 |
Track List |
* * * * *
「サラヴァ!」 : 高橋ユキヒロ (1978年6月リリース)
「サラヴァ!」は高橋ユキヒロのソロ・デビューアルバムです。
この人はサディスティック・ミカ・バンド解散後はミカバンドの残党と共にサディスティックスとして活動したり、様々なセッションやスタジオワークをこなしていました。
このアルバムは当時にしては珍しい欧州志向の強いアルバムで、お洒落でエレガントな雰囲気に田舎の少年は憧れたものでした。このアルバムは今でも私のバイブルです。
Yukihiro Takahashi - Mood Indigo -
Takahashi Yukihiro - Saravah! -
|
「サラヴァ」 : 高橋ユキヒロ |
|
 |
Track List |
* * * * * * * * * * *
さて、この企画はこれで終わりではありません。
カセットテープで保有している過去音源をCDに置き換える事業を進めているのですが、その一環として音源レビューをアップしたいと思います。
とりあえず、第1弾は高橋ユキヒロって事で、後日お逢いいたしましょう。
では、ごきげんよう。
追記:
企画倒れの気配がぎゅんぎゅんします!!
脂汗で腋の下がぬるぬるします! 激しくぬるぬるします!!
Talちゃん来日記念、もとい、Jeff Beck来日記念エントリです。
Talちゃんの、あ、いやJeff Beckのライブを体験出来ない、「悔しい思い」をぶつけてみました。
ってか、オッサンの昔語りでスイマセン。
Jeff Beckの曲を初めて聴いたのは小学生の頃です。我が家に4チャンネルステレオという画期的な家電がやって来た70年代初頭の頃です。で、そのステレオの(多分)おまけで付いてきた4チャンネルオーディオ用のサンプルLPにJeff Beckの「Going Down」が収録されていました。それがJeff Beckとの出逢いであり、少年と洋モノロックとの遭遇でした。その時期と前後して、ラジオでStevie Wonderの「迷信(Superstition)」を聴いたことで洋楽に目覚たのですが、この辺は自分でも因縁を感じずには居られません。(詳細はStevie Wonder(Wikipedia)の豆知識を参照。)
私にとって、音楽体験の起点はStevie WonderとJeff Beckだったんですね。
さて、Jeff Beckの音楽史は、The Yardbirds ~Jeff Beck Group (1st, 2nd ) ~ Beck, Bogert & Appice ~ ソロ(~現在)となるのですが、今日は第2期Jeff Beck Groupの音源を集めてみました。
Jeff Beck Groupは「第1期」と「第2期」に分けて語られる事が多くて、これは構成メンバーと音楽性の特徴から便宜上使用される呼び方です。
「第1期」ではヴォーカルにRod Stewart、ベースにRonnie Wood(現 The Rolling Stones)を迎えて、いかにも60年代後半的なブルース・ロックをやっていました。当然、その頃のことは私は判りません。
「第2期」になると、黒人音楽からの影響をモロに受けたファンク・ロックを展開。Jeff Beckとの出逢いのきっかけである「Going Down」も「第2期」の楽曲です。
Jeff Beckの音源は当時のFM番組からエアチェックしたショボいカセットテープが殆どだったのですが(*1)、この第2期Jeff Beck Groupだけは大人になってからCDを買って音源を補完しました。(失われた過去を取り戻す作業の始まりです。)
第2期のメンバーは
Jeff Beck (G)
Bobby Tench (Vo,G)
Max Middleton (Key)
Cozy Powell(Dr)
Clive Chaman(B)
というラインナップ。
このバンドのキモはCozy Powellのドカドカ鳴るドラムと、Max Middletonの気の利いたプレイに、Clive Chamanの渋いランニング・ベース、そしてBobby Tenchのソウルフルな歌声ですね。要はメンバー全員がイイんです。
あれ、Jeff Beckは?
いや、周りのメンバーがJeff Beckの音を引き出し、さらに引き立てているようにさえ感じるんですよね。
特にMax Middletonのピアノとフェンダー・ローズがJeff Beckの尖ったギターと実に上手く絡むんです。
Jeff Beckのwikiをご覧頂くと解ると思うのですが、自分の我侭からバンドのメンバーと衝突して何人ものミュージシャンをクビにしてきたJeff Beckが、同じメンバーで2年に渡って活動し、オリジナルアルバムを2枚もリリースするなんて奇跡ですからね。
でも、結局、第2期を始める前にプランを立てていて実現しなかったTim BogertとCarmine Appiceとのバンド結成の夢が忘れられず、彼等と組むためにこのバンドは空中分裂してしまいます。しかし、Max Middletonに対する信頼は厚かったのか、その後ソロなってからの「Blow By Blow」「Wired」という歴史に残る名盤に参加しています。
| Ice Cream Cakes | Highways |
| Going Down |
New Ways / Train Train |
Definitely Maybe
|
「Rough and Ready」 : The Jeff Beck Group |
|
 |
Track List |
|
「Jeff Beck Group」 : The Jeff Beck Group |
|
 |
Track List |
Jeff Beckをよく聴いたのは第2期 ~ Beck, Bogert & Appice まででした。ソロになった75年以降は急速にジャズ色が強まり、インストゥルメンタルがメインになっていきます。ロックの新たな方向性を示て、歴史的な名盤「Blow By Blow」や「Wired」をリリースし、攻撃的でカッコ良いプレーを展開しては居ましたが、付いて行けたのはその辺りまで。80年代以降は聴かなくなってしまいました。
ただ、還暦を迎えてお爺ちゃんになっても「妙な枯れ方」をするのではなく、音の尖り具合にさらに磨きを掛ける辺りは、間違いなく「人間国宝」級だと思いますね。
さて、DVD「
注釈:
(*1)今回、地元のTSUTAYAでCDを借りまくりました。70年代のアルバムが意外と豊富。
(*2)『ドラマーのサイモン・フィリップスによれば「彼は自分では曲は書きません。彼はソロ・アーティストなんですが、音楽を創るには他の人達に依存せざるを得ないんです」 』 via.ジェフ・ベック(Wikipedia)
追記:
こんなのを見つけたので貼っておきます。
昼休みの時間になると、放送室にあるレコードから適当にBGMを掛けていたんだが、どれもこれもつまらない音楽ばかりで全然楽しくなかった。
何がポール・モーリア、”エーゲ海の真珠”だ!!
何が魅惑のムード音楽だ!!
昼休みってのは自由な時間なんだ!!
だから、家からこっそりとカバンに忍ばせてきた”このレコード”を掛けたんだ。
別に何かが変わるとは思わなかったが、とてつもなくワクワクした。
Detroit Rock City : Kiss
一曲掛け終わらないうちに先生が血相を変えて放送室に駆け込んで来て、
「そんなレコード掛けるんじゃない! 放送室にあるレコードを掛けろ!!」
って怒鳴られた。
僕はムッとしつつも、束の間の爽快感を味わったので満足しては居たのだが、「放送室にあるレコードを掛けろ」の一言にカチンと来たので、レコード棚に入っていた”ぴんから兄弟”の「女の道」を掛けた。
すると、また先生が怒鳴り込んできて、「今日のお昼の放送は中止だ!!」と一方的に打ち切りを命じられた。
後日の昼休みの時間。その先生が「このレコードを掛けろ」と言って、自分の趣味なのだろう、映画音楽を集めたようなムード音楽のレコードを持ってきた。
何を掛けろとは言われていないよ。だから「エマニエル夫人(*1)」のテーマ曲を掛けたんだ。
痛快だった。
以上は何の脚色も無い、中学生の頃の本当の話。
今日、20世紀少年を観て来た。
冒頭のエピソードが自分の体験と全く一緒で、何かジーンと来た。
20th Century Boy : T-REX
(BGM 「20th Century Boy」 : T-REX)
注釈:
(*1)40代以上なら誰でも知っている魅惑のソフトポルノ映画。大人から子供まで、全国の男性たちが主演のシルビア・クリステルにシビれた。
先日の事。
Perfumeの3人と同い年の姪(女子大生)が実家に遊びに来ていて、食卓を囲んで談笑中に彼女の口から「四人囃子」という単語が発せられて、思わず〆張鶴純米吟醸「純」を噴出しそうになってしまった。
学生時代にバンドをやっていた両親(姉[key]、義兄[dr])の影響かと思いきや、なんと、彼氏が70年代のレジェンドバンドヲタとの事だった。”はっぴいえんど”を始め”めんたんぴん”やら”スモーキーメディスン”やら色々と名前が出てくる。叔父さんでもリアルタイムで体験していない伝説のロックバンドが沢山。
いや、ちょっと待て! あのなあ、若いんだからもっと若い音楽を聴けよ! テクノ・ハウスで夜遊びしろよ。なんなら叔父さんレコード回すぞ!(ズレてる) それとも叔父さんが野外レイヴに連れ回そうか?(勘違いしている) おお、そうだPerfumeを聴け!!
なんて事を口走りそうになったがここは堪えて、温故知新も正しいなと考えたのさ。
* * * * * * * * * * * * * * * *
今回紹介する四人囃子のアルバム「一触即発」は中学生の時に同級生からレコードを借りてカセットにダビングした。その頃は耳にする音楽全てが新しくて、ワクワクしながら色んな音源を聴いていたっけ。さすがにカセットテープも痛みが激しくなったので、先日限定紙ジャケ仕様のCDを購入した。
四人囃子は日本語プログレロックとの初めて出会いだと思う。
凛とした佇まいのクリーンなギターと優しいフェンダーローズ(?)の音色が、一転して怒涛のリズムと先鋭的なギターと攻撃的なハモンドオルガンの音色に変わる。ドラマティックな展開。そう、何かの映像作品を観ているかのような音世界だ。
このアルバムを聴くと何故か暑い夏の情景が目の前に広がる。レコードを借りたのが夏休みだっただけの事かも知れないが、大きな欅に群がる蝉の声が聴こえてきたり、杉の木立に沿って伸びる長い坂道を汗を掻きながら歩いている自分の姿が見えてくるんだ。多分それは記憶に刷り込まれた歌詞の世界観に拠るものだろう。
|
「一触即発(+2)」<紙ジャケット仕様盤> : 四人囃子 |
|
 |
[hΛmaebeθ] |
四人囃子は日本のロックの黎明期に素晴しい痕跡を残したバンドだが、その卓越した演奏力と緻密に構成された楽曲の素晴しさはもちろんだが、末松康生の詩の世界がとても良いのである。特に「空と雲」「一触即発」の風景や心情の描写が好き。そのまま心象風景を表わしているのだろうか?
しかし同時に、とても観念的な詩世界でもあり、中学生の自分には十分理解できなかった。「おまつり」ではおろしたてのバラ色のシャツを着てお祭りのある街に出かけたのは良いけど、ボコボコにされて、、、と言う内容。大人になった今、それは学生運動が盛んだった頃の内ゲバの様子を表わしているんだという事にようやく気付いた。
四人囃子 : 「おまつり」 (於:'73 日比谷公会堂)
四人囃子 : 「空と雲」 (Yonin-bayashi - Sora to Kumo, 1974) audio only
(BGM 「空と雲」 : 四人囃子)
Gino Vannelliです。
Perfume繋がりでこのブログに流れ着いた20代以下の皆さんは「?」でしょうね。あなたの親御さんも若いころに聴いていたかもしれない。
ジノ・ヴァネリ(Gino Vannelli) と言います。シンガーソングライターです。今日は名前だけでも憶えて帰ってください。(あれ、これって以前も同じ事をやった記憶が、、、)
さて、なんで今「ジノ・ヴァネリ」なのかと言うと、最近ヘビーローテーションになっている曲(*1)があるのですが、それを聴いていて「あれ? この曲調は何かに似ている。何だろう?」と気になり出しました。それで、あれこれ思い巡らせているうちに、ジノ・ヴァネリの「Brother to Brother」が頭の中に鳴り始めて「コレだ」と。でもって、久しぶりに聴いてみたらまさしくビンゴでした。それからアルバムを聴き直しているうちに、30年経っても色褪せない程の楽曲の先進性に驚いてしまって、アナログLPを取り込んでMP3に変換してiTunesで聴きまくっています。
ジノ・ヴァネリの楽曲を知ったのは、この「Brother to Brother」が最初で、高校生の時ですね。その頃はフュージョン(当時はクロスオーバーと呼んでいた)にハマりかけていた時期で、NHK-FMの音楽番組で出会って衝撃をうけました。
ジノ・ヴァネリの曲世界って一言で言い表わせないんですよね。ファンク、ソウル、ジャズ、ポップス、ロック(それもプログレ)から、それぞれのカッコ良い部分を取り出してごちゃ混ぜにしたような感じ。それで居て、とてもメロウなバラードもこなす懐の深さも併せ持っていて、時にはエモーショナルに、時にはハートフルに歌い上げるジノの歌唱力も素晴らしい。そこには、ジャンルで括る事が馬鹿らしくなる様な音楽センスと楽曲のクオリティがあります。ルックスもロック・アイドルのようにセクシーで男前だしね。外見で判断すると完璧に(良い意味で)裏切られるという、どこかの3人娘のような存在です。
ただ、この類まれな音楽性はジノ本人だけによるものではなく、彼の兄弟達、ジョー・ヴァネリ(キーボード、編曲)とロス・ヴァネリ(作曲)との共同作業によるもの。従って、「ジノ・ヴァネリのサウンド」と言うよりは「ヴァネリ・ブラザーズのサウンド」と言った方が正しいかもしれないですね。
|
「Brother to Brother」(1978) : Gino Vannelli |
とてもメロウなAORバラード「I Just Wanna Stop」は全米トップ10入り。この曲のヒットのおかげでジノ・ヴァネリはAOR系アーティストとして語られる事が多いが、本当は変態フュージョンの人なんだ。
「River Must Flow」は渡辺香津美がKYLYN(*2)のライブでヴォーカルに矢野顕子をフィーチャしてカバーしています。これは必聴ですね。
やっぱ、一番はタイトル曲の「Brother to Brother」ですね。ジャズ、ロック、ファンクのエッセンスを濃縮して混ぜ合わせて、70年代プログレ的な曲構成でドラマティックに仕上げた名曲っす。まさに変態フュージョン!
途中の構成部分で聴く事のできるタイトなドラム、ブリブリのシンセベース、ドラッギーかつスペーシーなシンセと言った音のキーワードはそのまんま、今のプログレッシブに繋がるな。
さて、こんなに持ち上げといて、その後私の音楽史の中でジノ・ヴァネリはどうなったかと言うと、80年に発表された「Nightwalker」が結構AOR色が強くなって、以前の変態フュージョンぶりが薄れてしまい、結局それ以降あまり聴かなくなってしまったのね(爆)。
ジノ・ヴァネリは今でもコンスタントに作品を発表しているようです。
ところでYouTubeって凄いね。まさか映像が在ると思わなかったんで、記念に貼っておく。
なんと「Brother to Brother」のCMスポット
Appaloosaライブ版。むっちゃ70年代! VIVA 70年代!
コレは最近なのかな?
Metropole Orchestraとのコラボレーションによる「Brother to brother」
(BGM 「River Must Flow」 : Gino Vannelli)
注釈:
(*1)「6pm (Simon Grey Synthesizer Mix)」:Kings of Tomorrow。後日エントリをアップ予定。
(*2)「KYLYN」は日本の70年代フュージョンシーンを語る上での最重要ユニットですね。坂本龍一の初期作品に興味が有る人はチェック済みか。「I'll Be There」はスバラシい。
追記:
アレだね、ムービーを見てみたら、「セクシーで男前」と言うよりは「太目の兄ちゃん」だったね(爆)。アルバムジャケットは凄く男前に写っているんだけどね、濃ゆいけど。葉加瀬太郎? かつての岡村靖幸?
| 01 | 2025/02 | 03 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
困った事にPerfume成分が多目です。彼女達の親御さんとは間違いなく同世代です。ちなみにP.T.A.会員です。
ホントに御免なさい。
御用命は「lstd_rd の yahoo.co.jp」まで。